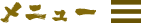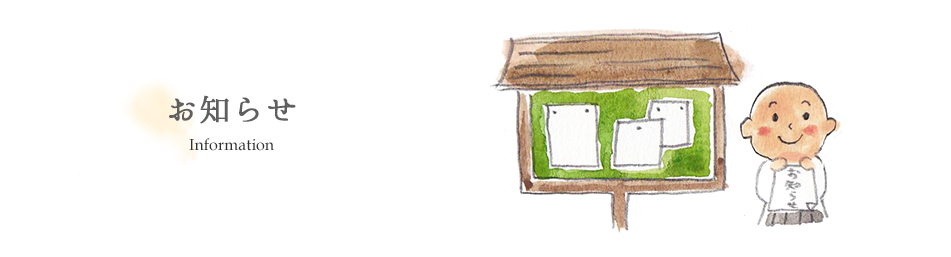お知らせ一覧
放てば手に満てり
2022-05-6
放てば手に満てり
囚われているものから離れなさい、という言葉です。
すべての人間は、何かに囚われています。お金、名誉、地位、自分、異性…。
自由な境地を求めるより、まず、囚われを握っている手を開きなさい、という教えです。
自分は、何に囚われているのか。何にこだわり、何に引っかかっているのか。
とても難しいことですが、それを手放した境地が、本当の自由です。
足るを知る
2022-01-20
洪福寺の石庭に、『吾れ唯だ足るを知る』と彫られた水盤があります。ワレ タダ タルヲ シル。
与えられたもので満足する生き方のことです。充分あっても、もっと欲しい、もっと欲しいでは、いつまでも貧しいままです。
裸で生まれて来ました。あの世に持って行けるものは何もありません。今あるものに感謝して、不足どころか、自分には多すぎると人に分けてしまう。こんな人を豊かな人といいます。
途中と家舎
2022-01-12
臨済録に『途中と家舎』という公案があります。『途中に在って家舎を離れず』という一節と、『家舎を離れて途中に在らず』という一節です。
途中に在って家舎を離れず。途中とは修行のこと、家舎は悟りのことです。修行をしていて、悟りを離れない。つまり途中に在って家舎を離れずとは、悟りの中での修行ということです。
皆さんは、この迷いの世界から悟りの世界に抜け出ようとして、坐禅の修行をしています。それがすでに悟りの中での出来事だというのです。
しかし、迷いから悟りへ到る、も、修行して悟りの世界に行く、も、すでに相対に分かれています。迷いと悟り。修行と悟り。二つが対立しています。
こう二つに分かれたら中道を行くのが仏教です。たとえば、趙州の無字。これは有るか無いかに分かれています。そこで中道を行く。ただ中道とは中間にはありません。一方に成ったところが中道です。修行と悟りなら、修行に徹したところ、そこが中道です。坐禅がうまく組めないと、一所懸命に坐る初心の坐禅が中道を行っています。
以前、海と波の話をしたことがあります。海と波は、平等と差別です。
この海と波で坐禅の境地の変化を現わせば、『波は波』から『波は海』になり、ついに『波はただ波』となります。
修行前は、波は波、概念の波です。言葉で名付けて、逆に言葉に騙されています。
悟った後は、波はすべて三昧の海です。これが途中に在って家舎を離れないところ、悟りの中での修行です。
長養すると波はただ波になります。これが家舎を離れて途中に在らず。もう何処にもいません。悟りにも尻を据えない。
皆さんはすでに出来上がっています。悟りの中での修行です。せっかく出来上がっているのに、皆さんの思いがそれを邪魔しています。何とかしようとして、思いを思いで、分別を分別で離れようとしています。コップの泥水を澄まそうとしてかき混ぜている。手を出すだけ濁ってしまいます。
三昧は働きです。その逆は、考えること、思うことです。三昧は一方向きです。しかし、この頭は振り返ります。
以前、妻がものを考えずにいることができる、と言った方がいます。その方の奥さんは、考えることではなく、働いているのです。家舎を離れて途中に在らず、を実行しています。ただ自分が一体になっていることに、一体なので気が付きません。三昧の状態にあるので、振り返らないから気づけません。自覚のない仏です。
自己と世界は、本来一体なので自覚がないのが普通です。禅僧の多くは、悟りの自覚なく働いています。普段、空気の存在に気がつかないかないようなものです。
ただ仏の働きだけが、そこにはあります。これが無心です。
愛別離苦
2021-10-13
これは、お釈迦様のころの実話です。
昔、インドにゴータミーという女性がいました。結婚をして、男の子を生んで幸せに暮らしていたのですが、ある時その子が亡くなってしまいました。それを受け入れられないゴータミーは、町中の家をまわり死んだ子の薬を求めました。そんな中、ある人からお釈迦様のところへ行くように言われ、お釈迦様を訪ねました。
お釈迦様はゴータミーに、今まで一族から死者を出していない家からケシの実をもらって来るよう言いました。喜んだゴータミーは、町中をまわりますが、死者を出していない家などありません。ゴータミーも「死なない人はいない」と気づきました。その後、ゴータミーはお釈迦様の弟子となり、出家したそうです。
家族の死を『愛別離苦』と言います。愛する人と別れなければならない苦しみです。お釈迦さまは四苦八苦の一つとしています。
家族との別れは簡単には受け入れることはできません。受け入れられない気持ちを無理になくそうとせずに認めてあげてください。今はつらい思いも、いつか美しい思い出になることと思います。
地獄と極楽
2021-10-12
仏の教えを簡単な物語にしたものが説話です。『エンマさんの招待』という説話があります。ある人がエンマさんに地獄と極楽を覗かせてあげると招待された話です。
まずは地獄からと覗いてみると、部屋の真ん中においしそうなうどんが入った大鍋が置いてあります。その周りを沢山の人が囲んでいますが、その人たちの片手には長い箸が結び付けられています。うどんをすくって食べようとすると、箸が長いので、うどんは自分の後ろに行ってしまう。どんなに頑張って食べようとしても、うどんは口には入らず、ガリガリにやせ細っている。これが地獄かと震え上がったそうです。
次は極楽はと覗くと、やはり部屋の中央にうどんの鍋があり、その周りを沢山の人が囲んでいる。片手には長い箸が結んである。なんだ地獄と同じかと思っていると、その人たちはすくったうどんを、向かい側の人に食べさせてあげている。自分は向かいの人に食べさせてもらう。皆福々と太り、ニコニコしていたそうです。
地獄と極楽は、おかれた状況は全く同じです。ただ、他人を一番に考えるとそこが極楽になり、自分のことばかりだと、そこが地獄になるようです。心したいものです。
欲しいからあげるへ
2021-09-12
最近、何かで読みました。エンマ大王はどうやって死者の善悪を調べるのか。生前人にしてもらった事を、天秤秤の片方にのせて、もう片方にしてあげた事をのせます。してもらった事の方が多いか、してあげた事の方が多いか。してもらった事の方が多い人は地獄へ、してあげた事の方が多い人は天国へ。簡単に調べられるそうです。
ほとんどの人が、してもらった事の方が多いのではないでしょうか。特に男性はしてもらう事に慣れています。時間になれば、食事やコーヒーが出てくる。部屋や衣類は放っておいてもきれいになっている。天秤がしてもらった事に傾いています。
欲しい欲しいともらってばかりいないで、あげることにハンドルをきる時です。
まずは、家族にお茶の一杯から・・・
七仏通誡の偈
2021-09-12
仏教には、八万四千の教えがあると言われます。結局、何の教えなのかと、よく聞かれます。
七仏通誡の偈というものがあります。
悪いことはしない。
善いことをする。
自分の心を清らかにする。
これが仏教である。
これだけの教えです。
唐の時代、道林禅師が詩人の白居易の質問に答えています。
仏教の大意とは何でしょうか?
悪い事をせず善いことをする。
そのようなことは、三歳の幼児でも言えるでしょう。
三歳の子供でも知っているが、八十歳の老人でも実践するのは難しい。
悪い事をせず善いことをする。簡単で当たり前なことですが、実践するのはなかなか難しいことです。他人のためになる事を、何かしてみましょう。
生まれる前に帰る
2021-09-11
人が亡くなることを仏教では、帰元とか帰空と言います。元へ帰る。空に帰る。
仏教では人の死を帰ることととらえます。どこへ帰るのか。生まれる以前のところへ帰ります。
その世界では、この小さな身体は無くなりますが、代わりに世界すべてになります。
良寛さんの歌にこういうのがあります。
形見とて 何か残さむ
春は花 夏ほととぎす 秋はもみじ葉
死の前に形見を乞われた良寛さんが、自分は死んでいなくなってしまうが、その代わりにこの世界すべてになると答えた歌です。これは、良寛さんだけのことではなく、故人も同じです。
ですから、春に美しい花を見たら故人を思い出してください。夏にきれいな鳥の声を聞いたら、故人を思い出してください。秋に色ずく紅葉を見たら故人を思い出してください。故人はそこにいらっしゃいます。
白木の位牌
2021-09-11
葬儀で使う位牌を白木の位牌と言います。
白木の位牌の頭には、帰元と書きます。帰元とは、元に帰るということです。人は死んでどこに帰るのかと言うと、生まれる前に帰ります。私たちは、そこから生まれて来たのです。
こんな歌が残っています。
阿字の子が 阿字のふるさと立ち出でて
また立ち帰る 阿字のふるさと
阿字というのは、命の根源・仏のことです。
私たちは、仏から生まれ、仏に帰ります。生きている間のあれこれの悩みも、みな仏の中の出来事です。安心して悩めば良いのです。
知恵と智慧
2021-07-4
『ちえ』には二つあります。知恵と智慧です。
知恵は言わばカミソリで、よく切れますが、
薄く欠けやすく出来ています。
一方、智慧は厚く重く出来ている斧のようなものです。紙は切れませんが、木を切ることが
出来ます。
この二つは、使うところが違います。
歳をとるということは、薄いカミソリが厚い斧になっていくようなものです。新しいことは若いカミソリにまかせて、斧は人生という木を相手にしましょう。