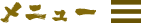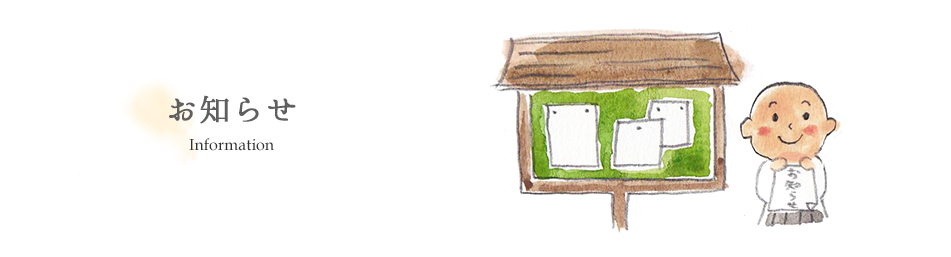「一口法話」一覧
五蘊
2019-07-29
五蘊 世界や自分を構成している五つの要素
色・受・想・行・識
色・・物質
受・・感受
想・・想念
行・・意志
識・・意識
世界や自分を作っている、五つのものを五蘊といいます。これは簡単に言えば、物と心です。物と精神と言っても同じです。ここでは五蘊を自分を構成している五つの要素ととらえます。
この五つの要素ですが、お釈迦様は何故五蘊を説かれたのでしょうか。私の勝手な解釈かも知れませんが、お釈迦様は別に自分を作っているものを教えたかったのではないと思います。五蘊のどれにも、主体となるべきものはないと、自己など本当はないと教えたかったのではないでしょうか。物質は自己ではない、感受も意識も自己ではない。五蘊すべて自己ではないと。
大昔、中国に渓仲という車造りの名人がいました。その渓仲があるとき車をバラバラに分解して何事か考え込んでいた。渓仲は一体何をしていたのか。車をただの木片の集まりにして、そのどこに車の本質があるか考えていたのです。結局どこにも車の本質などない。集めて形作ってはじめて車が現れる。現れたものを仮に車と呼ぶだけです。
五蘊も同じです。自分をばらばらにして、肉体と精神に分ける。その精神も四つに分解する。そのどこに自己が有るか。肉体をばらばらにして、精神もばらばらにして、詳しく調べてみたが何処にも自分はいない。自己の中心は見つからない。それらを集めたものを仮に自分と呼ぶだけです。
達磨安心という話が伝わっています。後に達磨大師の法を継いだ恵可が始めて達磨さんにあった時の話です。その時恵可は「私は不安で一杯です。師よ、私を安心させてください」とうったえたそうです。それに対して達磨さんは「その不安な心を持って来なさい。安心させてあげよう」と仰った。その後、恵可は心を探し続けたが、どこにも心はなかった。そこで達磨さんに「どこを探しても心はありませんでした」と言った。達磨さんはそれを聞いて「君を安心させ終わった」と言った。恵可はそこで悟ったそうです。
心などどこにもない。これが無我の教えです。お釈迦様は、無我を弟子たちに伝えたいがために五蘊を説いたのだと思います。
四苦八苦
2019-06-9
四苦八苦
生老病死の四苦に愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五蘊盛苦の四つを足したものを四苦八苦という。
最初の四苦、生老病死は生き物としての人間の苦しみ。愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦は社会的苦しみ、五蘊盛苦は前の七つの総括と考えられる。
・生苦・・・生まれる苦しみ。
生きる苦しみではなく、生まれる苦しみ。生まれるのがどうして苦しみなのか。
生まれる以前は、自己は世界とひとつであった。世界そのものであった。それに肉体と精神いう枠組みを与えられるのが、生まれるということ。世界と一体の海からの自分というものの波立ち。
生まれたばかりの赤ん坊には、多分まだ分別は無い。母親を認識するのが、最初の分別。それから5年経ち、10年経ち、世界はこのようにバラバラに分かれてしまい、本来無かった自我まで形成されて、あたかも有るように見えてしまう。
・老苦・・・老いていく苦しみ。
齢をとり、足腰が弱り、眼は遠くなり、歯は抜け、今まで普通に出来ていた事が出来なくなる。だんだん体が思うようにならなくなる。
・病苦・・・病気の苦しみ。
動く事も難しくなり、機械につながれ、だんだんやせ細ってゆき、死を考えるようになる。
・死苦・・・死の苦しみ。
自我が消え去る恐怖。本来死ぬとは、また一体の世界に還る事なのだが、この肉体と精神という枠組みに囚われた我々は、そこに自我という無いものをあたかも有るように思い、その自我を失うことを恐れる。肉体と精神という枠組を使う主体と考える自我は、妄想であり、錯覚である。
・愛別離苦(あいべつりく)・・・愛する者と別離すること
家族や知人、どんなに大切な人ともいつかは分かれなくてはならない。最終的には、必ず人は死によって引き裂かれる。
しかし死とは無になることではない。全てになることである。そこを良寛さんは、形見とてなに残すらん 春は花 夏ほととぎす 秋はもみじ葉 と歌った。自分は死んでも春は花になり笑おう、夏はほととぎすとして鳴こう、秋はもみじとして色づこう。という意味です。良寛さんは死んで世界になっている。
・怨憎会苦(おんぞうえく)・・・怨み憎んでいる者とも交わらなければならない
仕事をしていれば、誰もが思うことです。また親戚関係、ご近所の関係、知人の関係、とにかく人間関係のあるところには、全てこの苦しみがついてきます。
何故他人を嫌うのか。多分お互い我を張り合っているから。自我をぶつけ合っているから。本来なかった自我を、成長とともにあるように錯覚した自我のぶつけあいが原因。
・求不得苦(ぐふとくく)・・・求める物が得られないこと
私たちには、あれが欲しいこれが欲しいと欲があります。美味しいものが食べたい。ブランドのバックが欲しい。海外旅行に行きたい。しかし、その多くはかなえられない。
高邁な願いであっても、かなえられない事が多い。たとえば平和。世界のどこかで人と人が殺しあっている。人種が違うから、宗教が違うからと戦っている。日本人のほとんどが、平和を願ってもそれはかなわない。求不得苦、求めても得られない。
・五蘊盛苦(ごうんじょうく)・・・存在の苦しみ。
この世界に、肉体と精神という枠組みを与えられ、私たちは生まれて来てしまった。海から波立って生まれ来てしまった。そして、本来ない自我も年齢とともに発生して、世界はこのように分節した存在になった。
これは元一体の海だったものが、存在という波になってしまったことが、原因である。存在する事、あること、それ自体を仏教は苦と捉える。
しかし、良く考えれば、波は海で出来ている。この肉体という波も、精神という波も、みな海で出来ている。その海を仏という。我々は、仏の波立ちなのである。そこに仏教の救いを観るべきであろう。
食事五観の偈
2019-06-9
五観の偈
一には功の多少を計り彼の来処を計る。
第一には、この食事がここに来るまでに、どれだけの人や自然の力をいただいたか、よく考えます。
この一椀のご飯も、大地の恵み、水の恩恵、光が降りそそいで、やっとお米ができます。もちろん農家の力をかり、それが運送され、お米屋さんが精米してくれます。最後にそれを調理してくれる人が居ます。それらの人や自然の恵みでこの一杯のご飯がここにあります。これはすごい事です。あだやおろそかには出来ません。
二には己が徳行の全闕(ぜんけつ)を忖(はか)って供(く)に応ず。
第二には、果たして自分にこの食事を頂くだけの徳があるだろうか。
私たちは、自分のお金で買った物は、自分のものだと、どう使おうと勝手だと思っています。コンビニのおにぎりなどは、百数十円で買えます。あれだけの人の手を煩わせながら、それをお金で数えます。しかし、禅寺ではそれを自分の徳で数える。はたして自分にそれだけの徳があるかどうかと。
三には心を防ぎ過貧等(とがとんとう)を離るヽを宗とす。
第三には、心を守って、貪りなどから離れます。
まず禅寺では好き嫌いを言わない。美味い不味いを言わない。出してもらったものを、ありがたく頂く。やれこの食材はどこそこの物だの、少し固いの柔らかいのとも言いません。それは貪りになります。
四には正に良薬を事とするは形枯(ぎょうこ)を療ぜんが為なり。
第四には、食事は薬と同じである。修行する体を守り、健全な精神を維持する為のものである。
美味しいものの食べすぎで、体を壊しては、本末顛倒です。程よいものを、程よく頂く。腹も身のうちです。質素なものを腹八分目。ただ道場では、ものが残せない。全部ありがたく頂く。信者さんの家に行くと、食べきれないほどのご馳走が並んでいる時が有ります。始めてのことですが、今の禅僧は食べ物を残します。もちろん食べない皿にははじめから手をつけません。豊かになった時代には、こういうことも起こる。
五には道業を成(じょう)せんが為めに当(まさ)に此の食(じき)を受くべし。
第五には、仏道を成就する為にこの食事をいただきます。
食べる為に働くのか、働く為に食べるのか、という質問が有ります。食べる為に坊さんをしているのか、修行する為に食べるのか。修行する為に食べるのにきまっています。坊さんは飯拾いの方法ではない。そして最後には仏道を成就したい。これが僧侶の誓願です。
この五つを修行道場では、食事の前に毎日読んでいます。我々禅僧の理想です。
悪口は毒蛇である
2018-09-11
悪口は毒蛇と思え、受け取るな
ある日、お釈迦様が弟子たちと托鉢をしていると、「俺たちは働いているが、お前たちは何もしない。まるで乞食じゃないか」と罵倒されました。
それを聞いてお釈迦様は、「言いたいことはそれだけですか」とすぐに立ち去りました。
不満に思う弟子たちにお釈迦様は、「あなた方は、誰かが毒蛇を手渡してきたら受け取りますか?」と尋ねました。そして「受け取らなければ、その毒蛇は、渡そうとした者の手元に残るだけである」とお説きになりました。
理不尽な悪口を言われたら、それを毒蛇と思って受け取らない。それが仏の教えです。
ストゥーパ
2018-07-26
ストゥーパ(塔婆)
ストゥーパとは仏塔のことで、仏様を供養するため、インドで建立されたものです。
仏教が日本に伝わった時にも、仏塔が建立されました。法隆寺や興福寺などの五重の塔です。時の権力者が財力を尽くして建立しました。日本中の五重の塔はみなストゥーパです。
そのストゥーパを漢字にしたのが卒塔婆です。今では仏様や先祖を供養するために、私たち庶民でも建てられるようになりました。法事や施餓鬼で建てる塔婆、あの一本一本に仏塔建立と同じ功徳があるのです。
貫くもの
2018-01-27
去年(こぞ)今年 貫く棒の 如きもの 虚子
この句を鎌倉駅で見た川端康成は背骨を電流が流れたような
衝撃を受けたと言っています。
この「貫く棒」とは何でしょうか?
ある人には信念であり、ある人には生き様そのものでしょう、
さて、あなたの「貫く棒」は何でしょうか?
命のバトン
2017-10-8
けさ秋や 見入る鏡に 親の顔 鬼城
朝鏡の前に立ち、ギョッとすることがあります。自分の姿に親の面影を見るからです。
この命は両親から受け取ったものです。両親は祖父母から、祖父母はまたその親からと、想像もできない過去から受け継がれ、今は自分が握っている命のバトン。
それを仏教では仏心といいます。仏心一つだけを貰い受け、仏心を生き、仏心に帰る。みな仏の中の仏の出来事です。
私はどこへ去るのか?
2017-05-6
我が生 いずこより来たる 去って いずこにか行く
良寛さんの言葉です。自分はどこから生まれ、死んでどこに行くのか?
晩年の良寛さんはこう歌っています。
形見とて 何か残さん 春は花 夏ほととぎす 秋はもみぢ葉
自分は死んでも桜として咲き、ホトトギスとして啼き、紅葉となり色づく。
自然と一体になった素晴らしい境地です。
今を生きる
2017-01-26
咲くも無心 散るも無心
花は嘆かず 今を生きる
坂村真民さんの詩の一節です。私たちは過ぎた日々を後悔したり、自分の行く末を不安に思ったりして生きています。
しかし、過去は戻りません。未来はまだ来ていません。私たちが生きているのは、今だけです。
花のように無心に、今を精一杯生きましょう。
怒りと憎しみ
2016-09-18
人間の感情の中で、特に苦しいものが、怒りと憎しみの感情です。
心の中にある怒りや憎しみにどう対処したら良いか?という質問を多くの方から受けます。
仏教では、その心の調え方をこう教えています。
怒りや憎しみの感情を素直に受容し、その変容を待つ。つまり、
・怒りや憎しみには、もともと実体がない。
・ちょうど鏡に映った姿のようである。
・心の鏡に怒りや憎しみが、映れば映ったまま、おこれば起こったまま、やめば止んだままにしておく。
・時とともに、心は静かで平安な状態に変わって行く。
時間のかかる大変な行為です。しかし、怒りや憎しみを抱いている相手の変化はまず望めません。自心を変える、これが仏の教えです。