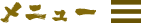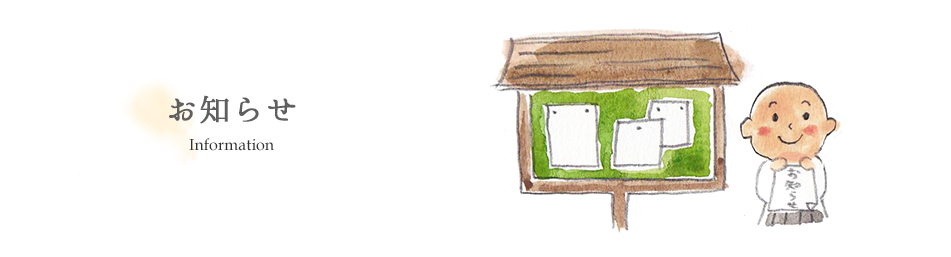「一口法話」一覧
和顔愛語
2020-09-7
和顔愛語とは思いやりの心です。笑顔や優しい言葉で他人に接する態度のことで、布施のひとつとされています。
世間はコロナウィルスで大騒ぎです。中には、罹患した方や医療従事者に厳しく対する方もいるようです。どんなに注意を払っていても罹ってしまうのが、このウィルスです。ここは思いやりの心の出番です。
和顔愛語の心で、笑顔や優しい言葉で人と接しましょう。他者への思いやりが、自分に対する執着を薄め、自分の心を調えることにもつながります。
八正道
2020-02-14
自分なりに八正道を解釈したものです。
八正道を正定に至る道とみるだけでなく、最後の正定により、初めの正見も深まるという、循環構造としてとらえました。
正見
そのまま見る。 己の見解を入れずに見る。
正思惟
思惟のない状態。 無心。
正語
言語の分節作用をよく理解する。
なおかつ普段の言葉遣いに注意する。
正業
作為のない行為。
普段の行為にも注意する。
正命
本来、すべての仕事は正命である。
自分の仕事に成りきること。
正精進
成りきる努力。徹する工夫。
正念
自己の見解を入れないで行為する事。
分別、解釈、思慮せずにありのままにある。
正定
成りきった境地。徹した境地。
六根
2020-02-5
六根(六つの感覚器官)
眼・耳・鼻・舌・身・意
眼に対しては色があり、耳に対しては音があり、鼻に対しては匂いがあり、舌に対しては味があり、身体に対しては接触感があり、意識に対しては存在があります。外の世界に対する六つの感覚器官が六根です。
人間は生まれる時、この六根だけを持って生まれてきました。真理を知りたければ、この六根の働きに任せきる。ころころと六根の動き働くままに任せきる。本当に心の手を放して、ただ六根の働きのままにある。
今の山梨県塩山市に向嶽寺という小さな本山があります。そこの抜隊得勝禅師という方に『塩山かな法語』という本があります。抜隊得勝禅師は、「見る者は何物、聞く者は何物」という公案で弟子たちを導きました。ただ見る者は何物、聞く者は何物と工夫する。
さて、何が見ているのか、何が聞いているのか。見る者は誰ぞ、聞くものは誰ぞ。寝てもさめても、見る者は誰ぞ、聞くものは誰ぞ、と。正解などありません。ただ、誰ぞー誰ぞーと己に問うているうちに、己が大きな?マークになります。三昧の?マークです。すると、答えは質問にあった、ということが分かり、そこに解決があります。
日日是好日
2020-01-26
日日是好日。普通「ひびこれ こうじつ」と読みますが、禅語では「にちにち これ こうじつ」と読みます。
昨日は良い日であった。今日も良い日だった。明日も良い日だろう。毎日毎日良い日・・・と取りがちな語ですが、この句はそんなに甘い言葉ではありません。江戸時代に活躍した禅僧、白隠禅師はこの句に対して次のような言葉を置いています。
「雨が続いて米がとれない。昨日は葬式、子供は病気、一日も良い日がない」
苦しみや悲しみに成りきった境地が、日日是好日なのだとこの言葉は教えてくれます。
主人公
2020-01-25
普通、この言葉は物語の主役を指します。しかし、禅語では見聞きし、考える主体を『主人公』と呼びます。
昔中国に瑞巌和尚という方がいました。変わった方で、毎日自分のことを、主人公ーーと呼び、自分ではいと返事をしていたそうです。そして、はっきりしていろよーと呼び、またはいと返事をして、人に騙されるなよーー、はいはいと一人でしゃべっていました。
この瑞巌和尚、実はとても立派な方で、ふざけて一人芝居をしていたのではありません。この方は、本当の自分を呼んでいるのです。心を呼んでいるのです。主人公ーーと。
前に『不識』の解説をしました。自分の心は振り返っても探せません。ここにこうして働いているのに、探すと見つからないのが心ですと。自分の主体『主人公』も同じです。振り返ってもそこにはいません。呼んでいるものが呼ばれているものだからです。だから振り返らずに主人公ーーと。成りきって、はい。はっきりしているかーー、はい。最後の人に騙されるなというのは、自他の分別をするな、ということで、自他を分けるなよーー、はいはい。ということです。
禅の要諦は、振り返らずに成ることです。見ずに成る。そこに『主人公』はいます。
不識
2020-01-24
この語は『無功徳』と答えた達磨さんと武帝の問答のつづきです。
いろいろ問答を重ねますが、武帝は納得しません。そしてついに最後の質問をします。「私の前にいるあなたはだれですか?」 そう問われただるま様は、
不識、知らん、と答えました。これは別に質問をはぐらかしているわけではありません。
考えてください。今見ているものは何か、聞いているものは何か、考えているものはなにか。自分を振り返ってそれを探しても見つかりません。それはそうです、探しているそれが探されているのですから。
だから『不識』です。
探すと心はどこにもないのですが、今ここに働いています。探さないで成る、これが本当の自分の見つけ方です。
無功徳
2020-01-23
これは、達磨大師が中国に渡った時、武帝とかわした問答からきています。
武帝は、沢山の寺を建て、多くの僧侶を育てました、その功徳をインドから来た達磨様に聞いたのです。
その答えは、無功徳、功徳などない、でした。
ある障碍者のおかあさんがいます。立派な方で、教えられることが多いのですが、その方は何か人のために行って文句を言われると、「ああ、よかった」と思うそうです。お礼などを言われると反対にがっかりするそうです。一方通行の、見返りを求めない功徳です。皆さんも料理などして、家族から「まずい」と言われたら喜んでください。それが、無償の愛です。
無功徳
こういう境地に入りたいものです。
一期一会
2020-01-23
一生に一度の出会い、という意味です。
皆さんとは、毎月お会いしていますが、これが一期一会です。今回の今日ここでの出会いは一度きりです。それを大切にする。
俳人の松尾芭蕉にこんな俳句があります。
よく見れば 薺花咲く 垣根かな
私たちが、見逃しやすいところです。ナズナとはぺんぺん草です。また、いつでもお目にかかれると思ってしまうところを、俳人は見逃しません。一期一会で、
よく見れば 薺花咲く 垣根かな
今、ここを大切に生きる。これが一期一会の精神です。
願い
2020-01-18
願い
日本を
楽しい国にしよう
明るい国にしょう
国は小さいけれど
住みよい国にしよう
日本に生まれてきてよかったと
言えるような国造りをしよう
これが二十一世紀日本への
私の願いだ
坂村真民
これは、元日に書かれた真民の願いの詩です。二十一世紀の日本を、戦争のない楽しく明るい国にしたい。
令和の世の安寧を祈念いたします。
戒名のはなし
2019-09-4
お通夜で読むお経は、得度式と同じもので正式に仏の弟子になるお経です。自分の人生を懺悔し、仏を師とする事を誓います。
仏弟子になると二つの名前が与えられます。
一つが道号、一つが法名です。○〇□□信士や信女、○〇□□居士や大姉の〇〇が道号で□□が法名です。合わせて戒名といいます。
ちなみに私も得度式で師匠から、宗禅という法名をいただきました。道場での修行を終えて後、卓道という道号もつけて貰いました。坊さんは生きているうちに戒名をいただくのです。