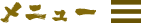無門関四十二則 女子出定(じょししゅつじょう)
2016-03-3
四十二則 女子出定(じょししゅつじょう)
世尊(せそん),昔,因(ちな)みに文殊(もんじゅ),諸仏の集まる処に至って,諸仏各(おのお)の本処(ほんじょ)に還るに値(あ)う。惟(た)だ一りの女人有って,彼(か)の仏坐に近づいて三昧に入る。文殊乃ち仏に白(もう)して云く,何ぞ女人は仏坐に近づくを得て,我は得ざる。仏,文殊に告ぐ,汝但(た)だ此の女を覚して三昧より起たしめて,汝自ら之を問え。文殊,女人を遶(めぐ)ること三帀(さんそう),指を鳴らすこと一下(いちげ)して,乃ち托(たく)して梵天(ぼんてん)に至るまで,その神力を尽くすも出(いだ)すこと能(あた)わず。世尊云く,仮使(たと)い百千の文殊も亦た此の女人の定を出すことを得ず。下方一十二億河沙(がしゃ)の国土を過ぎて,罔明(もうみょう)菩薩有り。能(よ)く此の女人の定を出す。須臾(しゅゆ)に罔明大士,地従(よ)り湧出(ゆうしゅつ)して世尊を礼拝す。世尊,罔明に勅(ちょく)す。却(かえ)って女人の前に至って指を鳴らすこと一下す。女人是に於いて定より出(い)ず。
無門曰く,釈迦老子(ろうす),者(こ)の一場の雑劇(ぞうげき)を做(な)す,小小を通ぜず。且(しばら)く道(い)え,文殊は是れ七仏の師,甚(なん)に因(よ)ってか女人の定を出すことを得ざる。罔明は初地(しょじ)の菩薩,甚としてか却(かえ)って出し得る。若(も)し者裏(じゃり)に向かって見得(けんとく)して親切ならば,業識(ごっしき)忙忙(ぼうぼう)も那伽(なが)大定(だいじょう)ならん。
頌に曰く,
出得(しゅっとく)出不得(ぷとく),渠儂(きょのう)自由を得たり。
神頭并(なら)びに鬼面,敗闕(はいけつ)当(まさ)に風流ならん。
まずは簡単に筋をお話しいたします。
釈尊在世の昔、文殊菩薩が多くの仏の集まる所に至ったが、諸仏の集会はもう終わってしまい、それぞれの仏国土に帰るところであった。そこに一人の女性がいて釈尊のそばで禅定に入っていた。文殊菩薩が釈尊に申し上げるには、なぜこの女性が仏の座に近づくことができて自分は近づくことができないのでしょうか。仏が文殊に告げて、君が自らこの女性を禅定から起こして質問してみなさい。そこで文殊菩薩が女性の周りを三回廻って指をぱちんと鳴らし、その女性を掌に乗せてこの世界のてっぺんまで連れて行くなど、様々な神通力をめぐらせたけれども、この女性を禅定から出すことができなかった。
そこで釈尊が仰るには、たとえ君が百人千人いようともこの女性を禅定から出すことはできない。この大地の下無限のところに罔明菩薩がいる。かれならこの女性を禅定から出すことができるであろう。罔明菩薩はすぐにそれを察して地上より現れて釈尊を礼拝した。釈尊は彼にこの女性を禅定から出せと勅命を下した。罔明菩薩が指を鳴らすと女性は禅定から覚めた。
そこを無門が評して、釈迦の親父は三文芝居を演じて人々を誑かした。さて答えてみよ。文殊菩薩は七仏の師である。なぜこの女性を禅定から出すことができなかったのか。罔明菩薩は修業を始めたばかりの菩薩である。なぜこの女性を禅定から出すことができたのか。ここの処がはっきりしたらならば、迷いの真っただ中で大禅定を得ることができるであろう。
そこを漢詩に詠って、出すも出さないも、どちらも自由自在である。文殊も罔明も、しくじりもまた風流である。
この女子出定の則は難透難解です。千七百則の公案のうちに三十八則難透難解というものがあります。これは大変難しい則ですがまあ聞いておいてください。
仏教では仏は理智(りち)を説き、祖師は機智(きち)を説くと言います。釈尊は理に訴えて教えを説く。祖師方は機(はた)らきでその智慧を説く。徳山の棒、臨済の喝。祖師は理屈を入れずに機(はた)らきで智慧を伝える。この公案は釈尊や文殊菩薩が主人公の公案ですから理智を説いたものです。この則はまっすぐ説くより、理智、理(ことわり)で説明いたします。華厳経に四法界(しほっかい)という教えがあります。四つの存在の世界、存在のありよう。華厳経ではこの世界を四つの見方で説明しています。理(り)と事(じ)の二つの関係で世界の在り方を説明するのが華厳の四法界です。
私たちがこの世界をただこう見る。禅定にも三昧にも入らずにただこう見る。そうすると柱は縦に敷居は横に、上には天井下には畳。自分があり世界がある。主観と客観が分かれた世界。そこでは世界は相対的に展開します。この分別された世界、これが事の世界、事法界(じほっかい)。般若心経の色即是空で言えば色の世界。これが一つの見方。
次が理法界(りほっかい)。皆さんが禅定で三昧に入ります。三昧の境涯では自分と世界、そういった区別がありません。無分別の処です。そこには何も在りません。無いということも無い。生死も迷悟も有無もない。心経でいえば空の世界です。これを理の世界、理法界といいます。この理と事をふまえて見ていただくとこの則も少し見やすくなります。四法界ですから後二つありますが、それは後で説明します。
禅ではよく円相(えんそう)を描きます。今の私たちはその円の底辺、事法界にいます。ここから修業を始めます。そして修業の末空に至ります、それが円の頂点です。そこには生死も迷悟も有無いも無い。そこが理法界です。円の半周です。まだ半周ありますね。釈尊は円を一回りなさった。文殊の智慧といいます。文殊とは釈尊の三昧、悟りの智慧を象徴しています。ですからこの円の頂点の理にいる菩薩であると、ここではそう考えておいてください。
世尊,昔,因みに文殊,諸仏の集まる処に至って,諸仏各の本処に還るに値う。惟だ一りの女人有って,彼の仏坐に近づいて三昧に入る。諸仏の集会に文殊菩薩は間に合わなかった。すると一人の女性が釈尊のそばで禅定に入っていた。この女性の禅定をどう見るか。文殊菩薩は理に徹した方、根本智を得た方です。その方が仏のそばに寄れない。一方女性は仏のそばで坐っている。これはどういうことか。
文殊乃ち仏に白して云く,何ぞ女人は仏坐に近づくを得て,我は得ざる。三昧も智慧も最も深い処に至っている、その自分が仏に近づけない、これはどういうことでしょうか。仏,文殊に告ぐ,汝但だ此の女を覚して三昧より起たしめて,汝自ら之を問え。文殊,女人を遶ること三帀,指を鳴らすこと一下して,乃ち托して梵天に至るまで,その神力を尽くすも出すこと能わず。釈尊は君が女性を禅定から覚まして質問してみなさいと。そこで文殊はさまざまに神通力を使ったが、どうしてもできない。ここは事と理の難しいところです。文殊は理の頂点、女性は坐禅を始めたばかり、事の世界にいる。
仮使い百千の文殊も亦た此の女人の定を出すことを得ず。下方一十二億河沙の国土を過ぎて,罔明菩薩有り。能く此の女人の定を出す。あなたが何人いてもできないことである。そこで罔明菩薩の出番です。この罔明菩薩は初地の菩薩です。仏教哲学では修業の階梯を五十二に分けている。その一番上にいるのが文殊菩薩、入り口にいるのが罔明菩薩です。修業を始めたばかりの彼なら女性を禅定から出せるであろうと。
須臾に罔明大士,地従り湧出して世尊を礼拝す。世尊,罔明に勅す。却って女人の前に至って指を鳴らすこと一下す。女人是に於いて定より出ず。すぐに罔明菩薩が現れて、この女性を禅定から出した。難しい則です。
無門曰く,釈迦老子,者の一場の雑劇を做す,小小を通ぜず。且く道え,文殊は是れ七仏の師,甚に因ってか女人の定を出すことを得ざる。罔明は初地の菩薩,甚としてか却って出し得る若し者裏に向かって見得して親切ならば,業識忙忙も那伽大定ならん。そこを無門は茶番と評しています。そして修行僧たちに詰め寄る。円の頂点にいる文殊が女性の禅定を覚ますことができず、初心の罔明がそれを行えたのはどうしてだ。これがこの則の一番大切なところです。
機縁が熟して自己の根源に気づく。これを見性といいます。これはすばらしい体験です。しかしここに住まってしまってはいけない。円の頂点に坐りこんでしまっては何の機らきもない。そこで百尺の竿頭に一歩を進める。
先ほどの華厳の四法のうち事法界と理法界を説明しました。あと二つ、理事無礙(りじむげ)法界(ほっかい)そして事事無礙(じじむげ)法界(ほっかい)。迷いの事と悟りの理が障(さわ)りなく交わる境涯、理事無礙法界。この存在の世界、事法界。三昧の世界、理法界。それが障りなく交わる。有りながら無い。無いながら有る。色即是空空即是色。日常生活の中で何の住(とど)こおりなく機(はた)らく。
その先に事事無礙法界。ここにはもう悟りのさの字もない。存在と存在がそのまま交差して何の障りもない。ここはもう擦りあげた境涯。円を一回りして元の木阿弥、一回りした大ばか者。これが華厳の四法界。
この女人は事の世界にいます。文殊は理の頂点にいます。理と事。この二人は相かなうことはありません。そこで女性と同じ境涯の罔明菩薩、この二人は縁が繋がります。相かなう。それが本則のところです。
そこで業識忙忙も那伽大定ならん。業識、迷いの炎が燃え盛っているそのままが、悟りの大禅定である。理事無礙法界そして事事無礙法界の境涯です。どうしても私たちは煩悩をなくして悟りに至ろうとします。坐禅中の雑念をなくして無心になろうとします。これが間違いです。心で心を何とかしようとしない。それは血で血を洗うようなもので、ますます心は紛糾します。放下著(ほうげじゃく)、放っておく。自分の心に手出しをしない。放っておけば清流のように流れている心に手を出さない。出てくる思いを掴まない。掴んだら素直に放す。坐禅の急所です。
頌に曰く, 出得出不得,渠儂自由を得たり。神頭并びに鬼面,敗闕当に風流ならん。出すとか出さぬとかいろいろやっているが、実はどちらも自在です。神さんの頭、鬼の面(つら)、何が出てきてもそのしくじりがそのまま風流。傀儡師(かいらいし)、首に掛けたる人形箱、仏出そうと鬼を出そうと、という歌があります。人形遣いが首の箱から鬼や仏を出して寸劇を演じる。そこで仏を出しても鬼を出しても、悟りを出しても迷いを出しても、文殊が出ても罔明が出ても、それは人形遣いが使っています。問題はその人形遣いです。
今皆さんは見たり聞いたり感じたりしています。坐禅は気持ちがおさまるなあ、しかしどうにも足が痛いなあ。仏が出たり鬼が出たりしています。こう私の声が聞こえるし、目の前のものが見える。ころころと皆さんの心は動いている。さて何が聞いていますか、何が見ていますか。皆さんじゃあない。しかし皆さんを離れてそれはない。言葉にすれば、仏心仏性、主人公。皆さんを機らかせている人形遣い。そこに目を付けてください。